コンテンツ案内
岩波新書 セレクト100 タイトル一覧
18 件

社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:367.2〉
暗黙のうちに男性主体で語られてきた歴史は,女性史研究の長年の歩みと「ジェンダー」概念がもたらした認識転換によって,根本的に見直されている.史学史を振り返りつつ,家族・身体・政治・福祉・労働・戦争・植民地といったフィールドで女性史とジェンダー史が歴史の見方をいかに刷新してきたかを論じる,総合的入門書.

社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:369.0233〉
イギリス独自の重層的なセーフティネットの中で,社会の「錨」のように今日まで働き続けてきたチャリティ.自由主義の時代から,帝国主義と二度の大戦をへて,現代へ.「弱者を助けることは善い」という人びとの感情の発露と,それが長い歴史のなかでイギリスにもたらした個性を,様々な実践のなかに探る.

社会学(国際・メディア)(法律・政治・行政)〈NDC10版:312.53〉
なぜトランプなのか? ニューヨークではわからない.アパラチア山脈を越え,地方に足を踏み入れると状況が一変した.明日の暮らしを心配する,勤勉なアメリカ人たちの声を聴く.そこには普段は見えない,見ていない,もう一つのアメリカが広がっていた.朝日新聞の人気デジタル連載「トランプ王国を行く」をもとに,緊急出版!

社会学(国際・メディア)(語学・コミュニケーション)〈NDC10版:699.39〉
今という時代を映す鏡でありたい──.従来のニュース番組とは一線を画し,日本のジャーナリズムに新しい風を吹き込んだ〈クローズアップ現代〉.番組スタッフたちの熱き思いとともに,真摯に,そして果敢に,自分の言葉で世に問いかけ続けてきたキャスターが,23年にわたる挑戦の日々を語る.

社会学(国際・メディア)(経済・経営・商学・観光)〈NDC10版:304〉
富の偏在,環境・資源の限界など,なおいっそう深刻化する課題に,「成長」は解答たりうるか――.近代科学とも通底する人間観・生命観にまで遡りつつ,人類史的なスケールで資本主義の歩みと現在を吟味.定常化時代に求められる新たな価値とともに,資本主義・社会主義・エコロジーが交差する先に現れる社会像を,鮮明に描く.

社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:316.81〉
一九四五年,朝鮮は日本の植民地支配から解放された.二〇一五年は七〇年の節目の年になるが,日本と南北朝鮮との間には今なお問題が山積である.在日朝鮮人をめぐる問題もその一つである.植民地期の在日朝鮮人世界の形成,解放から高度成長期以後の世代交代と多様化,そしてグローバル化へと至る現在までを扱う.

社会学(国際・メディア)(福祉)〈NDC10版:367.61〉
2013年,「子どもの貧困対策法」が成立した.教育,医療,保育,生活.政策課題が多々ある中で,プライオリティは何か? 現金給付,現物給付,それぞれの利点と欠点は? 国内外の貧困研究のこれまでの知見と洞察を総動員して,政策の優先順位と子どもの貧困指標の考え方を整理する.社会政策論入門としても最適な一冊.

社会学(国際・メディア)(法律・政治・行政)〈NDC10版:316.8〉
差別,侮辱,排除の言葉の暴力を,路上やネット上で撒き散らすヘイト・スピーチは,表現の自由として守られるべきなのか.深刻な被害は,既存の法や対抗の言説では防げない.悪質な差別の法規制は,すでに国際社会の共通了解だ.各国の経験を振り返り,共に生きる社会の構築へ向かうために.

社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:329.9〉
半世紀前にアジアからの留学生に出会い,その後,著者は,在日韓国・朝鮮人や留学生,労働者,難民などを取り囲む「壁」を打ち破るために尽力してきた.入管法の大幅「改正」,最新データを盛り込みながら,戦後補償,外国人学校など今も考えるべき問題についても語る.累計20万部のロングセラーの最新版.

社会学(国際・メディア)(経済・経営・商学・観光)〈NDC10版:366.29〉
「就職新氷河期」と言われる状況下,入学早々「就活」に振り回される学生たち.長く厳しい競争をくぐり抜けて晴れて正社員になっても働き過ぎ,過労が待っている.一方で非正規雇用の身には漏れなく貧困がついてくる…….理不尽極まりない近年の就職をめぐる若者の苦悩を克明に描き出し,その緊急改善を訴える.怒りと励ましの書.

社会学(国際・メディア)(福祉)〈NDC10版:304〉
希望は与えられるものではない,自分たちの手で見つけるものだ! でも,どうやって? 希望が持ちにくい時代に,どこから踏み出せばよいのだろう? 著者が出会った,たくさんの声に耳を澄ませて,希望をつくるヒントをさがし出す.「希望学」の成果を活かし,未来へと生きるすべての人たちに放つ,しなやかなメッセージ.
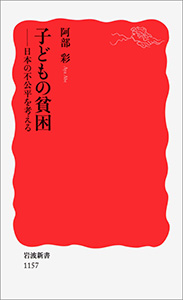
社会学(国際・メディア)(福祉)〈NDC10版:367.61〉
学力,健康,親との交流.大人になっても続く,人生のスタートラインの「不利」.OECD諸国の中で第2位という日本の貧困の現実を前に,子どもの貧困の定義,測定方法,そして,さまざまな「不利」と貧困の関係を,豊富なデータをもとに検証する.貧困の世代間連鎖を断つために本当に必要な「子ども対策」とは何か.

社会学(国際・メディア)(福祉)〈NDC10版:368.2〉
うっかり足をすべらせたら,すぐさまどん底の生活にまで転げ落ちてしまう.今の日本は,「すべり台社会」になっているのではないか.そんな社会にはノーを言おう.合言葉は「反貧困」だ.その現場で活動する著者が,貧困を自己責任とする風潮を批判し,誰もが人間らしく生ることのできる社会へ向けて,希望と課題を語る.
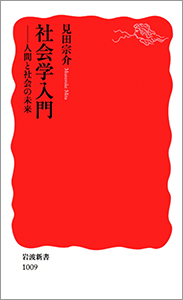
社会学(国際・メディア)〈NDC10版:361〉
「人間のつくる社会は,千年という単位の,巨きな曲り角にさしかかっている」──転換の時代にあって,社会学という学問は,いかに〈未来〉を構想しうるか.現代社会の絶望と希望を見すえ,その可能性をひらいてゆくための,探求の〈魂〉とは何か.分野の第一人者から初学者への講義として語られる,必読の1冊.
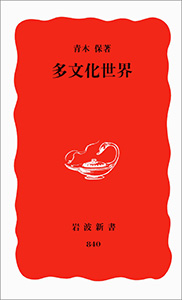
社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:361.5〉
イズムの角逐や苛酷な他者攻撃を経験してきた20世紀を経ながら,新世紀の世界は,宗教・民族間問題の先鋭化と同時に,グローバル化による画一化・一元化に直面している.真の相互理解や協調は可能なのか.その鍵となる「文化の多様性」の擁護をめぐって,理念・現状・課題を,文化人類学者としての豊富な経験・観察と共に具体的に説く.
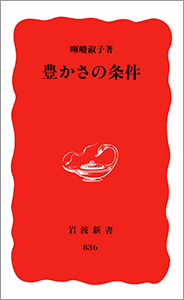
社会学(国際・メディア)(福祉)〈NDC10版:304〉
効率と競争の追求によって泥沼の不況から抜け出そうとする日本社会.だが,リストラ,失業,長時間労働,年金破綻など,暮らしの不安はますます募るばかりだ.子どもの世界も閉塞をきわめている.大好評の前著『豊かさとは何か』から14年.著者が取りくんできたNGO活動の経験をふまえて,真に豊かな社会とは何かを改めて考える.
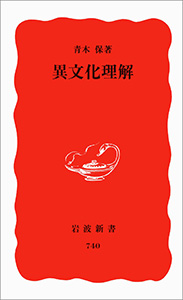
社会学(国際・メディア)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:361.5〉
IT,グローバリズムが進み,接触・交流が拡大した「異文化」を私たちは理解しているだろうか.異文化の間での衝突はいまなお激しい.また,ステレオタイプの危険性や,文化の画一化がもたらす影響も無視できない.文化人類学者としての体験や知見を平易に展開しながら,混成化する文化を見据え,真の相互理解の手掛かりを明示する.
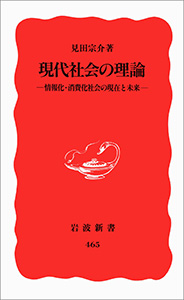
社会学(国際・メディア)〈NDC10版:361〉
「ゆたかな社会」のダイナミズムと魅力の根拠とは何か.同時に,この社会の現在ある形が生み出す,環境と資源の限界,「世界の半分」の貧困といった課題をどう克服するか.現代社会の「光」と「闇」を,一貫した理論の展開で把握しながら,情報と消費の概念の透徹を通して,〈自由な社会〉の可能性を開く.社会学最新の基本書.
