コンテンツ案内
ブルーバックス セレクト100 タイトル一覧
62 件

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:431.11〉
「読む元素事典」の決定版が、〈国際標準の最新元素周期表〉に完全対応!
元素とはなにか──?
・各元素の性質の違いはどう決まる?
・周期性があるのはなぜ?
・天然の元素と人工元素の違いとは?
・元素の数はどこまで増える?
・元素発見ランキングの第1位は誰?
・原子量などの重要データはなぜ変動する?
……ほか、元素番号1番「水素」から118番「オガネソン」まで、「万物の根源」をなす全元素を徹底詳説!
同位体の種類や存在比、半減期から電子配置、原子量まで。元素に関する最新数値を網羅。
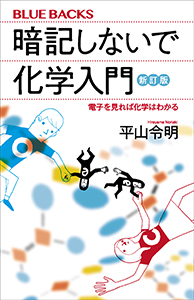
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:431.12〉
化学は暗記科目ではない。電子の動きを理解すれば、化学はすべて見えてくる。電子を共有することで、原子は結びつき、分子ができている。原子ごとの電子のふるまいがわかれば、化学はこんなにおもしろい! 授業がわかる。応用が効く。楽しくなる。わからない高校生、必読の入門書。化学嫌いなあなたの、化学の見方が変わります。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410〉
数学が苦手? それは「錯覚」です。――カオス理論の権威が説く、「本当は誰もが好きになれる数学の世界」!
多くの人は、数学という学問を誤解しています。難しい、とっつきにくい、役に立たない……
数学に対するこうしたイメージは、すべて「錯覚」です。人々の「素朴な思い」から生まれた学問なので、段階を踏んでいけば、誰にでも理解できるはずなのです。本書では、「測定」「計算」「論理」という基本から数学が持つ本質的な構造と役割を問い直していきます。“数学の階段”を登っていくと、あなたの想像を超える広い世界が見えてくるでしょう。数学が嫌いな人は、数学がちょっと好きになるはずです。もともと数学が好きな人は、これまでとは違う視点から、新しい数学の魅力を感じてもらえるはずです。
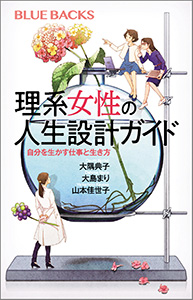
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(教育)〈NDC10版:407〉
理系の学部出身の女性は増えているとはいえ、理系であることを生かして活躍する女性はまだ少数派で、その実態はあまり知られていなことも。そんな「リケジョ」はどんな場所でどのような仕事をして、どのようなプライベートライフを送っているのか、先輩リケジョ達の体験やリケジョを取り巻く環境がどうなっているかを、レポートします。
大学での研究職、国立研究開発法人などの公的研究機関、企業も化粧品会社やライフサイエンス系のベンチャー企業などいろいろな業種を、また企業と大学両方での経験がある研究者など幅広く、さまざまな実例を紹介します。結婚や子育て、海外での経験とも絡めて、理系女子としての生き方をイメージする一助となる1冊です。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:455.8〉
名著復刊! 「大陸移動説」を世に問い、現代地球科学の端緒となった歴史的一冊を新書化! 永久不変と考えられていた大陸は、長い年月をかけてゆっくりと移動していた。常識を覆す「大陸移動説」はどのように生まれたのか。ウェゲナーが生涯をかけて取り組んだ研究の集大成となる一冊を、竹内均博士が全訳し、その後の地球科学の発展について鎌田浩毅博士の解説を加えた決定版。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:423〉
アイザック・ニュートンの代表作『プリンシピア 自然哲学の数学的原理』の全訳を全3巻で復刊。
最終巻となる第3編「世界体系」では、前2編で述べられた理論を、惑星、衛星、彗星などに適用し、太陽系内の諸現象が「万有引力」の法則によってまとめられる。また、全巻の結びとして書かれた「一般注」では、「私は仮説をつくらない」という有名な言葉とともに、自家の神学が説かれている。巻末注には、微積分の定理を使った別証明、原典では省略された証明の内容、現在の視点から見た物理的概念の解説がまとめられている。
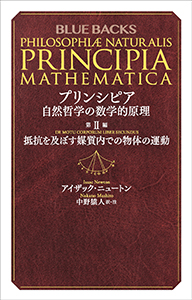
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:423〉
プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第2編 抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動
アイザック・ニュートンの代表作『プリンシピア 自然哲学の数学的原理』の全訳を全3巻で復刊。
第2編では、流体力学の諸問題が説かれている。ニュートンはまず、抵抗が速度に比例するものとして、あるいは抵抗が速度の自乗に比例するものとして問題を取り扱った。ついで、重力の作用の下での流体の釣り合いについて論じ、流体内における波動の研究がこれに続き、それから惑星運動の原因とされたデカルトの「渦動論」の検討へと進み、二、三の簡単な命題によってみごとにこれを否定した。
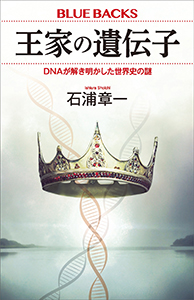
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(医学・歯学・薬学・看護学)〈NDC10版:467.3〉
駐車場から掘り起こされた遺骨は、シェイクスピアが嫌ったあの国王だった!? 530年前の人骨の正体を見破った手法とは? 遺骨から判明した「思いがけない真相」とは? ミイラから採取したDNA鑑定で、ツタンカーメンの母親が突き止められた!? 「勝者の歴史」が覆い隠した「王家の真実」を、最新生命科学が解明する! 歴史と科学が出会い、科学が歴史を書き換える──。
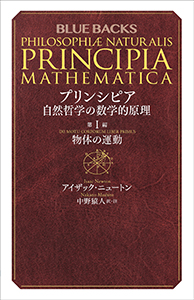
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(文学・文化・歴史)〈NDC10版:423〉
近代科学はここからはじまった! 運動の法則、万有引力の法則、天体の運行、……古典力学の基礎を築いた歴史的名著を新書化!
アイザック・ニュートンの代表作『プリンシピア 自然哲学の数学的原理』の全訳を復刊。出版当時から難解と言われた原典を、現代の科学者が「内容そのものの解明理解を目的」として翻訳。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(工学(機械・電気・建築))〈NDC10版:420〉
いやでも物理が面白くなる〈新版〉 「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか?
【電子版限定特典付】ほんとうは驚くほど面白い物理の話。理科コンプレックスがあっという間になくなる! 肉屋の肉はなぜ美味しそうに見える? 人工衛星はなぜ地球を周回できる? 朝日や夕日はなぜ赤い?カウンター・パンチはなぜ強烈? 圧力鍋はなぜ短時間で煮える? 紫外線が皮膚がんを起こすのはなぜ? 宇宙船内は無重力状態じゃなかった! ──すべての答えは「物理」が知っている!
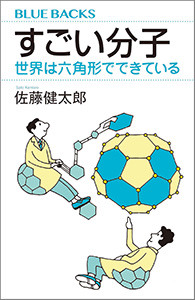
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:438.1〉
化学の象徴とも言われる六角形の芳香環。身近な物質にも広く存在するが、カーボンナノチューブやカーボンナノベルト、フラーレンなどのように、最先端の科学でも注目され続けている。大手製薬メーカーで創薬開発者だった著者が、六角形の物質の魅力にとりこになった化学者たちのエピソードを踏まえながら、芳香環のおどろくべき性質を紹介する。多くの日本人化学者たちが活躍する有機化学合成の最前線が楽しくわかる画期的入門書。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(環境学)〈NDC10版:451.85〉
地球46億年 気候大変動 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来
最先端研究でわかった気候変動を支配する「地球のからくり」。
隕石が絶え間なく降り注ぐマグマオーシャンの時代から全球凍結したスノボールアース、恐竜が繁栄した超温暖化時代、そして氷期、間氷期を繰り返す、直近の260万年にいたるまで地球の気候は激しく変動してきた。一見すると無秩序に激しく変動しているように見えるが、その変化には一定のリズムや規則性があることがわかってきた。鍵を握るのが、地球の公転軌道の変化がもたらす「ペースメーカー」と地球の表層における「炭素循環」だった!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:443.9〉
宇宙の「果て」になにがあるのか 最新天文学が描く、時間と空間の終わり
「宇宙の果て」に科学はどこまで迫っているのか。「ビッグバン」や「インフレーション」は本当にあったのか? 「ダークマター」「ダークエネルギー」とはいったい何なのか? 最新の宇宙物理学から見えてきた我々の住む宇宙の姿と、そこに残された大きな謎を詳細に解説する。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(教育)〈NDC10版:289.1〉
広中平祐氏の自伝的数学啓蒙書です。「学問とは何か」「学ぶとはどういうことか」「数学とは何か」など、数学や科学するときの最も大切な基本姿勢を教えてくれる1冊。広中平祐氏が特異点解消問題を解決して、1970年にフィールズ賞を受賞した経緯にも触れられていています。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:411.1〉
なぜ算数を学ぶのか――スキルアップである。鶴亀算、過不足算、仕事算、……いまではなんとなく解けてしまうかもしれない。その解法の背景には、論理的思考力が隠されている。問題を把握し、わかりやすい形に変換し、解決への道筋を計画し、実践する。これは、算数に限らずあらゆる問題解決に共通するプロセスである。あらためて算数の問題の解き方を学ぶことで、学生から社会人まですべての人に求められるスキルが養われる!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(医学・歯学・薬学・看護学)〈NDC10版:464.27〉
DNAの98%は謎 生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か
サルとヒトで遺伝子はほとんど同じなのに、なぜ見た目はこんなにも違うのだろう? ヒトゲノムのうち遺伝子部分はわずか2%。遺伝子ではない「98%」にヒトの秘密が隠されていた! かつてはゴミ扱いされた“ジャンクDNA”が生命の謎を解き明かす。
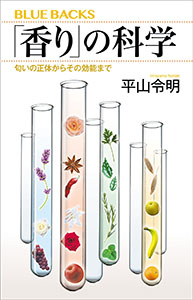
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(工学(機械・電気・建築))〈NDC10版:576.6〉
人類は何千年も前から香料を利用してきましたが、じつは「匂い」を感じるメカニズムや、その正体が何かということについては、長い間謎に包まれていました。自然にはどんな香りが存在するのか? 人は新しい香りをどのように作りだしてきたのか?アロマテラピー、香水、シャンプーや石鹸などの香りは、人体にどのような影響を与えるのか? 香りの神秘を最新科学で解き明かします。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:443.5〉
太陽の100億倍もの質量を持つ巨大ブラックホールは、強力な重力で光さえ飲み込む一方で宇宙でいちばん明るく輝き、光速にちかい速さの「ジェット」を放出しています。200年以上前に予言されながら、まだ誰も見たことのなかったブラックホールの姿が、最先端の天文学によって明らかになりつつあります。
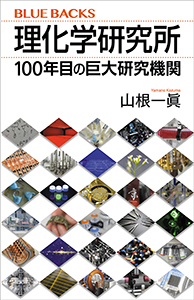
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(工学(機械・電気・建築))〈NDC10版:407.6〉
113番元素だけじゃない、スパコンからバイオ、脳科学まで、幅広い研究で基礎科学を支える日本最大の研究所「理研」。1917年(大正6年)に設立され、100年目を迎える今では450の研究室、3000人の研究者を擁し、全国に研究施設を持つ。ノンフィクション作家・山根一眞がつぶさに研究現場を訪ね歩き、今いったいどんな研究が行われ、研究者たちは何を目指しているのか、その全貌を明らかにします。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:450〉
東日本大震災を境に、日本列島は「大地変動の時代」に入ってしまった! 複数のプレートがひしめく恐るべき地理的条件にあるこの国で生き延びるには、「地学」の知識が不可欠だ。しかし、高校での履修率は低く、多くの人の地学リテラシーは中学レベルで止まったままである。ご存じ「地学の伝道師」が、地学の「おもしろいところ」「ためになるところ」だけを一冊に詰め込んだ、すべての日本人に捧げるサバイバルのための地学入門。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:412〉
142857と、先頭の1を末尾に回した428571。2等分して足すと、どちらも答えは999!(142+857、428+571)428571の先頭の4を末尾に回した285714でも同じ現象が!(285+714=999)ぐるぐる回る“ダイヤル数”のふしぎを生み出すのが素数!?「1÷素数」が描き出す定理と法則を探訪する、初等整数論への新しいアプローチ!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(工学(機械・電気・建築))〈NDC10版:453.4〉
活断層地震はどこまで予測できるか 日本列島で今起きていること
熊本、鳥取、福島沖──なぜ、大地震が頻発するのか? 地震の連鎖は「活動期」に入ったからなのか? 日本列島に走る活断層の数はなんと2000以上、次の地震を引き起こす「火種」は今もどこかでくすぶりつづけている──。活断層とは何か? 直下型地震はどうして起きるのか? 今知りたい疑問に答えます。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(工学(機械・電気・建築))〈NDC10版:431.53〉
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か 世界をリードする日本の科学技術
「人工光合成」は太陽ネルギーと水を原料にして、水素などの高エネルギー物質を創り出す技術です。温暖化の原因とさえる二酸化炭素を抑え、再利用することで、環境にもやさしいエネルギーです。日本人が発明したこの技術こそ、地球のエネルギー問題を救えると世界中から注目されています。2050年の実用化をめざすプロジェクトの全容をわかりやすく解説します。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:425〉
高校数学でわかる光とレンズ 光の性質から、幾何光学、波動光学の核心まで
本書では主に、光を光線として扱う幾何光学と呼ばれる分野を解説し、特にレンズの働きを明らかにします。光学機器として、現代において大活躍しているカメラやメガネ、そして望遠鏡、顕微鏡、それらのレンズに関する物理を基礎から解説していきます。高校数学の知識を身に着けていれば、現代光学の知識をひとつひとつ確実に理解していくことができます。定評のある「高校数学でわかる」シリーズの記念すべき10作目!!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.9〉
20世紀、急速に進化・発展したコンピュータの世界。コンピュータに計算させるためのプログラム、その基になるアルゴリズムの理論が誕生した。アルゴリズム、そして計算量の理論から生まれた「多項式時間(P)で解ける」とは。そして、「非決定性多項式時間(NP)で解ける」とはどういうことか。ミレニアム問題の1つ、現在でも未解決の数学の難問を、コンピュータの歴史からさかのぼって説明します。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:411.6〉
群の歴史は、方程式の研究に遡ります。1変数のn次方程式の解法について、古代バビロニアから、カルダノ、フェラリ、ラグランジュ、ルフィニ、アーベル、そしてガロアの群論へと発展します。本書は、高校数学の知識でも理解できるようにていねいに解説した群論の初心者のための入門書です。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:412〉
物語の主人公は、2種類の素数。「4で割って1余る素数」と、「4で割って3余る素数」。一方は「2つの整数の平方和」で表せるが、他方は表せない。一方はx^2+1の素因数に現れるが、他方は決して現れない。両者の無限性を証明したオイラーの巧みな方法とは? 2つの素数の個性がわかる、連分数や平方剰余の相互法則、ガウス素数とのふしぎな関係とは?
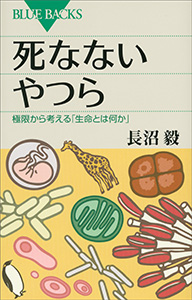
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:460.4〉
小さなチャンピオンたちが教えてくれること。生命とは何か? この根源的な問いに、私たちはいまだに答えることができない。ならば、極端な「エッジ」を眺めて考えてみよう。超高温、超高圧、高塩分、強放射線、強重力……過酷な環境をものともしない極限生物たちの驚異の能力と、不可解きわまる進化。そこには「不安定な炭素化合物」として40億年も続いた生命という現象の本質がある。
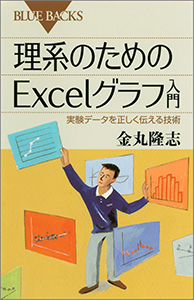
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(情報学)〈NDC10版:007.6384〉
理系のためのExcelグラフ入門 実験データを正しく伝える技術
実験で得た数値データを表すグラフは、誤解なく読み取れるように仕上げることが重要。これをExcelで実現するために必要なデータを正しく伝える技術について丁寧に解説する。軸ラベルや凡例、線の種類などの基本設定から対数グラフやヒストグラムなどの描き方まで、卒論やレポートなどに用いるグラフの質を飛躍的に向上させる知識が自然と身につく。
※本書は以下の環境を使い、機能を確認して執筆しています。「Excel 2010、Excel 2013(共にWindows 7)」「Excel 2007(Windows Vista)」「Excel 2003(Windows XP)」
※本書で掲載している画面はExcel 2010で使用したときのものです(Excel 2013、Excel 2007、Excel 2003でも操作できるように、紙面の許す限り補足を入れています)

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:455.8〉
図解・プレートテクトニクス入門 なぜ動くのか? 原理から学ぶ地球のからくり
よくわかるプレートテクトニクスの始まりから発展まで。プレートテクトニクスは、地球表面の岩石圏に見られるさまざまな構造や変動を解き明かす科学。地震はもちろん、火山ができるしくみから、高い山ができるしくみ、深い海底ができるしくみまで、地球のからくりが見えてくる。
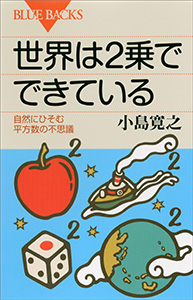
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.4〉
2乗を通して見る、深遠な数学と物理の世界。同じ数を2回掛けると現われる「平方数」には、数の「遊び心」や物理現象の秘密がかくれている。ピタゴラス、ガウス、フェルマー、リーマンら偉大な数学者の業績に見える平方数から、ガリレイ、ボーア、アインシュタインら偉大な物理学者が見いだした自然法則まで、平方数に秘められた不思議で深遠な世界をわかりやすく紹介する。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:414.12〉
ナポレオンやデカルトまで虜にした魅惑の図形。もっとも単純な多角形でありながら、紀元前の昔から数学者や歴史上の偉人たちを魅了しつづけた三角形。ピタゴラスの定理だけじゃない、シンプルな形に隠された美しくも不思議な性質の数々を紹介します。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:420〉
公式でひもとく自然の法則。高校物理でここまでわかる! 一見複雑な物理の世界をシンプルに表したのが公式。放り投げたボールの着地点の予測から、リニアモーターカーが走る原理、ICカードで改札口を通れるしくみまで、高校物理の公式で理解できてしまうのです! 役立ち感満点、大人だからこそ知って得する高校物理のエッセンスを、身近な現象と公式を切り口に解説。学び直しに最適化した知的実用書。
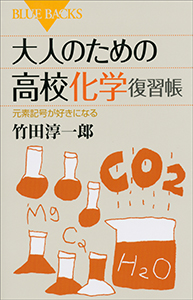
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:430〉
化学反応はどうして起こる? 高校化学でここまでわかる! 身の回りの物質の性質や反応のしくみを知るのが化学。電池に電気が蓄えられるのはなぜ? 洗剤に「まぜるな危険」とあるのはなぜ? 使い捨てカイロはなぜ熱くなるの? そんな日常の不思議が高校化学で理解できてしまうのです! 役立ち感満点、大人だからこそ知っておきたい高校化学のエッセンスを、身近な現象を切り口に解説。学び直しに最適化した知的実用書!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(医学・歯学・薬学・看護学)〈NDC10版:467.3〉
生命の設計図DNAが分子レベルで解読され、ゲノム工学技術が飛躍的な発展を遂げた現代、生命科学は文系理系を問わず社会の幅広い分野で不可欠の科学となりました。まさに分子が織りなす命の綾としての「新しい生命像」を、日本を代表する分子生物学者がその最前線から解き明かします。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:459.9〉
タンパク質もウイルスも結晶になるって、知っていますか? 美しさと純粋さの秘密に迫る。水晶、ルビー、ダイヤモンド、食塩、砂糖……、私たちのまわりには、多くの結晶があり、太古から私たちを魅了し続けてきました。それでは、結晶とは物質のどういう状態なのでしょうか? それは、純粋さと、化学結合と、対称性の素晴らしい自然の産物なのです。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:412〉
大学入試問題で語る数論の世界 素数、完全数からゼータ関数まで
自分自身以外の約数の和がその数になっている「完全数」。単純な規則から驚きの数列が生まれる「フィボナッチ数」。「ピタゴラスの定理」と面積157の直角三角形の秘密。リーマン予想につながる「ゼータ関数」。22n+1(2の2乗のn+1乗)の形をした「フェルマー数」は果たして素数を表すのか。大学入試問題を水先案内人にして、魅惑あふれる数論の世界に分け入る。
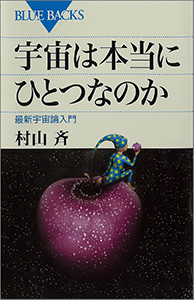
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:443.9〉
最新の理論と実験から迫る全く新しい宇宙観宇宙の90パーセント以上は得体の知れない暗黒物質と暗黒エネルギーからできている。その正体を探っていくと多くの次元と宇宙が見え隠れしているというのだ。急展開を見せる宇宙の最前線をふまえて「宇宙とは何か」を問い直す最新宇宙論入門。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:443.5〉
ゼロからわかるブラックホール 時空を歪める暗黒天体が吸い込み、輝き、噴出するメカニズム
アインシュタインの一般相対性理論が予言したおそるべき暗黒天体ブラックホールは、激しい論争の末にその実在が明らかになり、いまもなお人類に多くの難問を突きつけている。超巨大ブラックホールの形成、光り輝くガス円盤、噴出するジェットのすさまじいパワー、ホーキング放射による蒸発などを世界に先駆けシミュレーションで追究する著者が「絶対に誰にでもわかるように」と宣言して書いたブラックホール入門書の決定版!
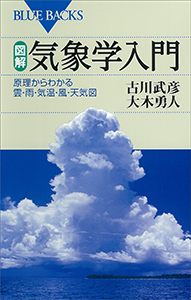
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:451〉
数十トンもある雲が落ちてこないのはなぜ? 高原は太陽に近いのになぜ涼しいの? ジェット気流って何? 高気圧や低気圧はなぜできるの? 日頃の疑問が氷解します! 原理がわかると、知らなかった気象の姿が見えてくる――気象と天気のしくみを原理から詳しく丁寧に解説した「わかる」入門書。やさしい語り口ながらも気象学用語の多くを網羅。気象予報士を目指すスタートにも最適。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:413.2〉
なるほど高校数学 数列の物語 なっとくして、ほんとうに理解できる
数字の並び方に秘められた謎を解く これが数列の面白さ。高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、数学入門シリーズ。数列の表し方から、等差数列、等比数列、数列の和、パズルを解くように推理する漸化式、頭を悩ます数学的帰納法までを、ゆっくりと説明します。数列の向こう側には、無限が見えてくる!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.79〉
85%の確率で勝って帰れるカジノ必勝法があるらしい。もちろん不正はナシ。いったいどんな方法? 一見難しそうな問題が思いもよらないシンプルな手法で一瞬のうちに解けてしまう――古今東西のパズルファンをうならせてきた愉快で奥深い数学の世界を楽しみながら、思考力に磨きをかけよう。
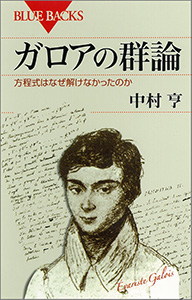
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:411.73〉
ガロア群を見れば、すべてが判る! 2次方程式の解の公式は、バビロニアですでに知られていた。3次方程式の解の公式は、カルダノ(タルターリャ)が発見した。4次方程式の解の公式は、フェラーリが作った。5次以上は解の公式が作れないことを、アーベルが証明した。しかし、5次以上でも解ける方程式はいくらでもある。なぜなのだろう? 20歳の若さで死んでしまったガロアが、それを明らかにし、どのように考えたのか。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.38〉
読みながら公式の意味と使い方をマスターできる。センター試験では、限られた時間の中で問題を正しく、速く解くという苛酷な作業が要求されます。羅列された公式をただ問題に当てはめるのではなく公式の本来持っている機能や働きを理解して使うことで、より公式の力が発揮できるようになるのです。入試問題の対策と攻略に役立つ公式集の決定版。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)(環境学)〈NDC10版:402.979〉
地球上の90.6パーセントの氷が南極には存在している。巨大な氷の塊である「氷床」の厚さは富士山の高さを超え、隕石が大量に見つかるポイントがあったり、氷の下には“幻の巨大湖”が存在していたりする。温暖化の懸念から南極への注目度はますます高まるなか、オゾンホールが南極に現れる仕組みから基地における最新の観測方法やその生活内容まで、“現在の南極”にまつわるエピソードを網羅した1冊。
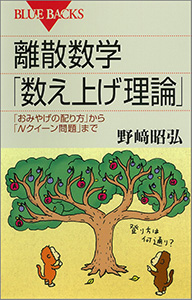
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.9〉
離散数学「数え上げ理論」 「おみやげの配り方」から「Nクイーン問題」まで
問題を解きながら、離散数学の考え方がわかる! すべての情報を「0と1」の組み合わせで表すコンピュータの普及で、重要性が見直されている離散数学。離散数学の中核にあるのが「数え上げ理論」である。予備知識のいらないやさしい問題で分割数、フィボナッチ数、カタラン数に触れたあとには、数え上げ理論の三種の神器である包除原理、差分方程式、母関数の理論を紹介。その奥深い魅力が、充分に味わえる。
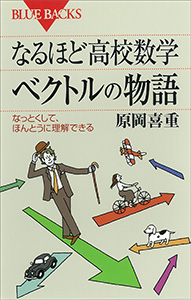
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:414.7〉
なるほど高校数学 ベクトルの物語 なっとくして、ほんとうに理解できる
高校の数学って、こんなに役に立つんだ! 基礎知識が全くなくてもベクトルが理解できる。高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、新シリーズ。ベクトルとはなにかから、ベクトルの計算、図形への活用、線形代数の入り口までを、誰でも理解できるように、ゆっくり語ります。ベクトルというのは、単なる矢印です。ただしその矢印を、足したり引いたり、2倍したり、あたかも数のように扱うことができます。ベクトルは、磁気や電気、重力など、自然界の力の理解には欠かすことができません。また、2次元や3次元の図形を調べるときにたいへん有用です。本書はベクトルについてまったく基礎知識がなくても、十分に理解できるように書かれています。
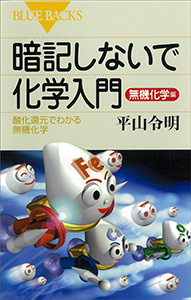
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:431.37〉
電子のやり取りを見れば、無機はわかる。「電子のやり取り=酸化還元」が無機化学を理解する鍵だ! 「電子のやり取り」のことを、化学では「酸化還元」と言います。暗記するしかないと思っていた無機化学は、実は「電子のやり取り=酸化還元」で、その大部分を、すんなり理解することができるのです。化学の「理屈と面白さ」がわかる、絶好の入門書。
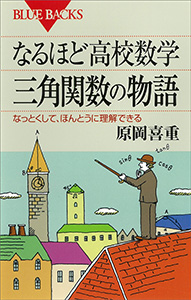
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:413.59〉
なるほど高校数学 三角関数の物語 なっとくして、ほんとうに理解できる
高校の数学って、こんなにやさしかったんだ! 「相似」さえ知っていれば大丈夫。三角関数が「まるごと」わかる。高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、新シリーズ。意欲的な中学生から社会人まで、教科書にはない、ほんとうの数学のおもしろさを味わおう。
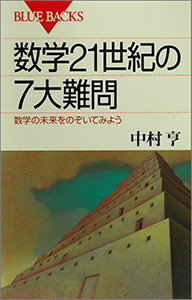
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.4〉
「リーマン仮説」「ポアンカレ予想」「ホッジ予想」「バーチ、スウィンナートン=ダイアー予想」「P対NP問題」「ヤン・ミルズ理論」「ナヴィエ-ストークス方程式」2000年5月、クレイ数学研究所はそれぞれ100万ドルの賞金を懸けて、21世紀に解決を期待する7つの未解決問題を発表した。この「ミレニアム賞問題」を、高校生でもチャレンジできるように解説した、数学ファン待望の本。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:426.5〉
エントロピーはなぜ増え続けるのだろうか? 熱の正体は? エントロピーの正体は? マクスウェルの悪魔はまだ生息しているのか? ブラックホールのエントロピーって? 物理ファン待望の「熱」の決定判。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:440.12〉
ノーベル賞学者が明かすニュートリノの世界。ニュートリノの質量がゼロでないとしたら。宇宙が生まれた1秒後の世界から、大統一理論の再構築まで、スーパーカミオカンデの最新データから宇宙の実像に迫る。
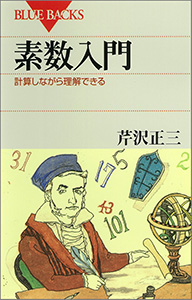
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:412〉
79の次にくる素数は? では、151の次は? 自分で計算できるはじめての初等整数論。1と自分自身以外に約数がない正の整数。たったそれだけの素数の性質から、整数論の世界をひもといていく。ガウス、フェルマー、オイラー、メルセンヌなど、数学の天才たちをとりこにした素数の魅力とは?

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:430〉
教科書や参考書ではわからない化学の醍醐味 「化学は暗記科目」だと勘違いしていませんか? 知識をひたすら詰め込んでも、うんざりするだけ。 大事なのは、「なぜ、どうして?」という疑問を大切にすること。素朴な疑問に真摯に向き合い、考え続けるうちに化学の面白さが自然にわかってくるはずです。 本書を読めば、あなたの化学の見方がきっと変わります。 こんな悩みはすぐ解消します!
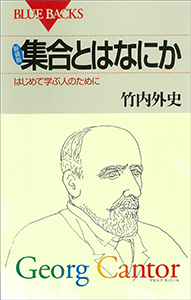
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.9〉
名著、新装復刊! 現代数学でどんな役割を果たしているのか? 「集合」抜きに現代数学は展開できない。集合とはなにかという問題は、新しい集合の公理の探究という問題をはらんで、現代数学の最も深い問題といってよい。集合概念がもたらす、深遠な謎、集合論の中に潜むロマンチックな創造の精神、これらを数学の訓練を経ていない人々に説明した名著にカントールの評伝を追加して復刊!
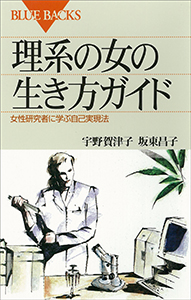
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(教育)〈NDC10版:407〉
先輩研究者の生活と意見。テーマの選び方から子育て期間の乗り切り方まで、楽しい研究生活のために必要な知恵! 結婚や子育ての経験が理系で生かせる。女性研究者の最大の障害とされる結婚や子育ても、その経験を男にはまねのできない強みにしてしまおう。積極的でスマートな研究生活を送っている、先輩女性研究者からの実感アドバイス。理系をめざす女性たちに贈る熱いエール!
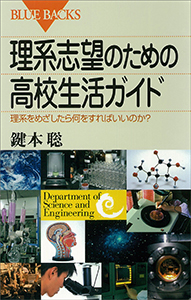
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(教育)〈NDC10版:376.4〉
理系志望のための高校生活ガイド 理系をめざしたら何をすればいいのか?
不安と悩みを一挙に解決! とにかくやるべきことが多い理系志望。何を勉強すればいいのか? 時間はどう使えばいいのか? 知りたいのは効率的で自分らしい高校3年間のすごし方。たんなる進学情報や受験勉強法を超えた、理系をめざす人への真のアドバイス・ブック!

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:429.6〉
物質の究極的構造とそれを支配する基本法則を探る素粒子物理学はどう発展してきたか。2008年にノーベル物理学賞受賞の著者が、トップクォーク発見後の視点から振り返り、将来を展望。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:410.4〉
自然には、楽しい数学がいっぱい。身のまわりの木や草花、古代の遺跡や絵画、本やカード……、さらには私たちの美意識までも、数学と深いかかわりをもっています。円周率、黄金比、ピタゴラスの定理、フィボナッチ数、フェルマーの大定理等々。自然と数学の不思議な関係を、楽しいエピソードで紹介します
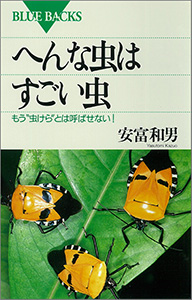
理学(数学・物理・化学・生物・地学)(農学(農・獣・畜産・水産))〈NDC10版:486〉
時に楽しい表情を見せてくれる虫たちのなかには、生いたちや暮らし、行動からみて「へんな虫」がたくさんいます。キノコを栽培したり、蜜をだす他の虫を飼育したり、自分の体を子に食べさせたり、超能力を発揮したり……。しかし、本書で取りあげる彼らのふしぎな生態こそ、数億年という歳月をかけて獲得された生き残り戦略であり、実は「すごい虫」であることのあかしなのです。彼らの生きざまに注目してください。

理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:412.2〉
フェルマーの大定理が解けた! オイラーからワイルズの証明まで
ついに解けた! どう解けた?「Xn+Yn=Znという方程式は、nが2より大きい自然数であれば、自然数解X、Y、Zをもたない」――フェルマーの最終予想とも呼ばれるこの問題は、問題の意味が誰にでもわかるほどやさしいにもかかわらず、アマチュアの数学愛好家はもちろんのこと、多くの著名な数学者たちの挑戦を、数100年ものあいだ退けつづけてきた。だが、ついに1994年、A・ワイルズがその証明に成功した。
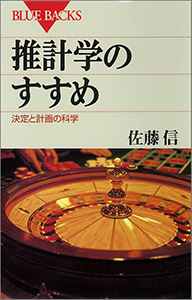
理学(数学・物理・化学・生物・地学)〈NDC10版:417.6〉
教養としての推計学的考え方!《決定の理論》合理的判断への道すじ《カンと経験》当てになるかどうか?《品質管理》無駄を出さない方法《比較と判定》とちらが上か?《原因と結果》本当に薬がきいたのか?《世論調査》正しい結果を出すには?
